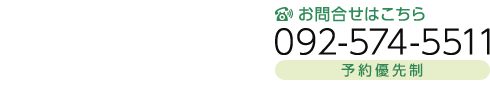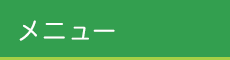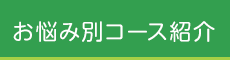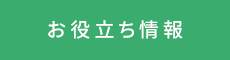今日は歩く時はどこに体重をかけて、意識して歩いた方が良いかの質問をいただきましたので、お伝えしたいと思います。
結論からいいますと、主に内踝(うちくるぶし)の下にあたりに体重をかけて、背中を意識して歩くのが良いと言えます。
その理由を説明すると、人間の足の骨(下腿)は脛骨と腓骨という2本の骨でできています。

大型動物の牛や馬などは重い身体を支える為に一本になっていますが、人間、犬、猫など小型動物は2本になります。
頸骨に身体が乗る方が安定します、なぜかと言うと脛骨の上に大腿骨そして骨盤、下に踵があるからです。
腓骨は補助的な骨になります。
解剖学的な骨の太さから考えても脛骨に8割、腓骨に2割というのが体重をかける理想です。
つま先から踝(くるぶし)。
踝(くるぶし)から踵骨(かかと)までの比率も約8対2になっています。
こうした構造的にも体重をかける割合も踵8割、つま先2割ほどが良いでしょう。

そして体重をやや内側にかけやすいように踵の骨はやや外側にあります。
・下の図は右足を後から見た図になります。

足裏には体重の負荷を分散する筋肉のアーチがあります。
足裏のアーチも親指側の方が大きく(土踏まず)内側の負担を軽減しやすくなっています。

足裏のアーチの事や脛骨の末端が内踝(内くるぶし)ということを考えても、やや内側に体重が乗る方が良いと思います。
そして主に踵に体重がある方が背中側の筋肉を使いやすくなります。つま先側に体重が載っていると、主に身体の前側の筋肉を使いやすくなり姿勢も悪くなり疲れやすくなります。
背中や臀筋、ハムストリング(太ももの後ろ側の筋肉)などの背中側の筋肉の方が何倍も強く、姿勢も良くなります。
下を向いて歩いたり、足を擦って歩くなどをしている方は、身体の前側の筋肉を使っていることが多いので疲れやすく姿勢も悪くなります。
姿勢が崩れている人や疲れやすい方はつま先や小指側に体重が乗っていたり使っていることが多いのです。
靴裏を見ると、つま先や外側が多くすり減っているかもしれません。
以上のことをまとめると、
内くるぶしの下あたりに体重をかけて、背中を意識して歩くのが良いと言えます。
このようにできるだけ骨に身体を乗せた方が、無駄な力を使う必要が無くなり姿勢も良くなり疲れにくくなります。
以上が整体的見地からみた、歩く時はどこに体重をかけて、意識して歩いた方が良いかの回答になります。
その他気になることやわかりづらいことなどありましたら、来院時やLINEにてご質問下さいね。